「みんなのお仕事相談所」では、ユーザーさまのご依頼の相場や製作期間、
契約書やお金に関する悩みを気軽に相談できるQ&Aコミュニティです。
違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
また、違反報告についてはよくある質問の「【共通】違反報告とは」をご確認ください。
ウェルクに端を発する一連の「パクリ」について、クラウドワークスはどう対応するつもりですか。
受付中
- 回答数
- 54
- 閲覧回数
- 7364
DeNAの「パクリ」による記事作成をサポートしたサービス提供会社として、クラウドワークスはどのように考えているのでしょうか。問い合わせの受け付け窓口が見つからないので、ここにポストします。
ランサーズはこの件で対応を始めたようです。
-----------
『ランサーズ、「仕事依頼ガイドライン」設置 “コピペ記事制作”の指示禁止など定める』
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1612/06/news080.html
-----------
私の知る限り、いまだにクラウドワークスからは何の反応もないように感じます。「ニュース」のページを見てもこの件に関して何のリリースもありません。
昨日6日もクラウドワークスから下記のような依頼情報が流れていました。
-----------
公開日 2016年12月05日
応募期限 2016年12月19日
仕事 ライティング(経験不問) » レビュー・口コミ
支払い方式 固定報酬制 予算 100,000円 〜 300,000円
納品希望日
求めるスキル
記事のジャンル 美容コスメ・ファッション
記事のテーマ 女性向けファッションメディア
記事数 20 記事
文字数(1記事あたり) 1500 文字 〜 2500 文字
記事単価 1000 円
文字単価 0.4円 〜 0.7円
-----------
私が一番奇異に感じたのは上記の欄外にテキスト作成の参考サイトとして「MERY」が上げられていたこと。
同サイトは本日7日公開停止予定(現在はまだ公開中)で、
すでに5日に公開停止のリリースがDeNAからされていたにもかかわらず、です。
記事の作成過程で問題ある可能性が高いサイトとして運営主体が認めたにもかかわらず、
「MERY」のような記事を作って欲しい、つまり、パクったテキストを欲しいと言っているに等しい依頼情報を、
クラウドワークスは流していたのです。
何のチェックもなくただ情報を流すだけなら、
“キュレーション”を名乗るパクリサイトとレベルは同じではないでしょうか。
企業市民として、まずまっとうなコンプライアンス構築を、
そして、このサービスを続けていくつもりなら長期的な視野に立ち健全な市場の育成を目指していただきたい。
※この投稿が無断で消されても証拠を公開しておくために、SNSにも投稿します。

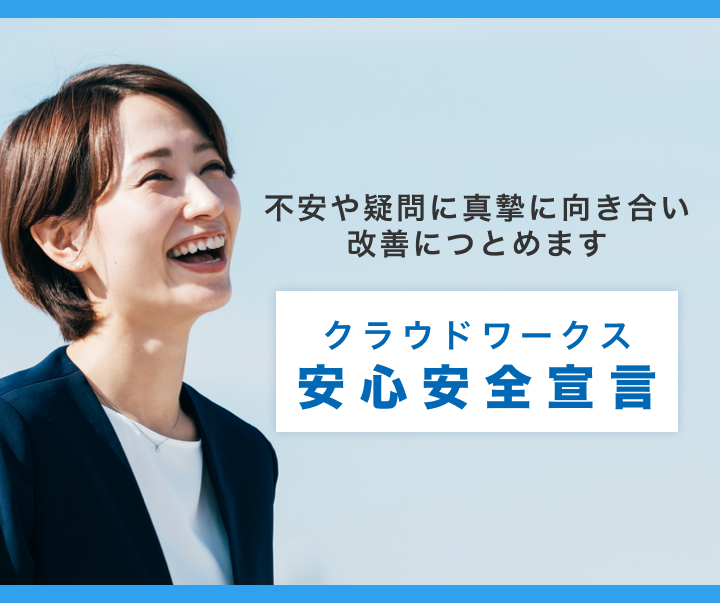
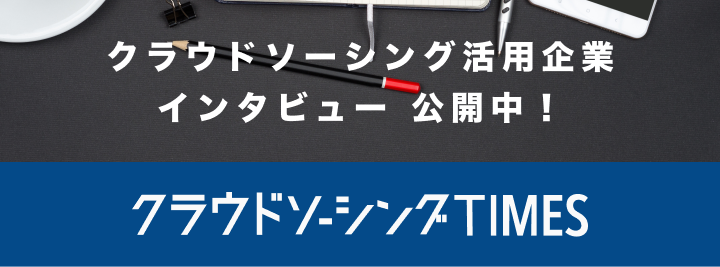
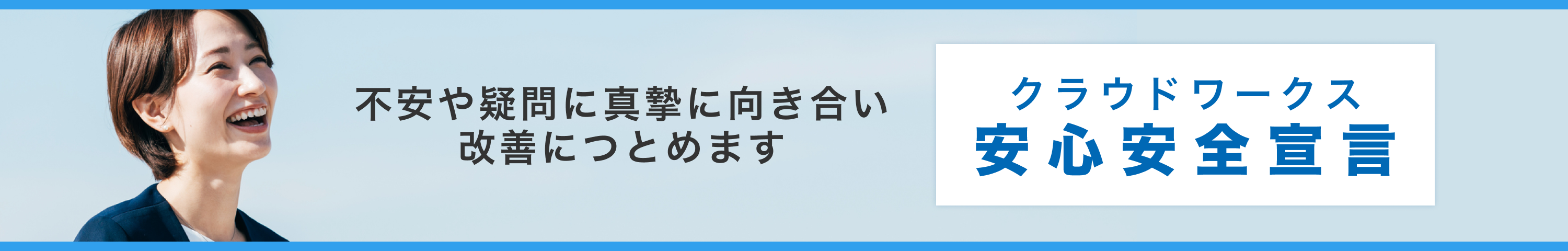
自動化されているから仕方ないですよ。
こちらではクラウドワークスからは返答されないようなので、直接問い合わせた方がよろしいかと思います。
https://crowdworks.secure.force.com/faq/FaqInquiry
上記URLから問い合わせできるかと思います。
>何のチェックもなくただ情報を流すだけなら・・・
以下まったく同意いたします。
ただ、こちらの「みんなのお仕事相談所」で、クラウドワークス運営の方からご回答があった例は、私は存じません。
明確な回答が欲しいものだとは思いますが。(期待を込めて注視します)
ちなみに皆さんがよく仰る「どこにあるのかわからない」お問合せ窓口のURLはこちらです。もっと分かりやすいところに明示してもらいたいものですよね。
https://crowdworks.secure.force.com/faq/FaqInquiry
長々と書いていたら、妖艶木苺さんと被ってしまいました。失礼しました。
皆さん、ありがとうございました。
いま、問い合わせの方にメール入れました。
しかし、導線を見ると、問い合わせされたくないのがミエミエですね(笑)
すみません。
私はコピーペーストで全てチェックされていますけれど・・・。
あとね、以前ここの相談所では、「全てコピーです。どう思いますか?」っていう相談がありました。
私の予想ですけれど、クラウドワークスに相談されても答えは「双方でお願い致します。」って言われそうですね。
今回の件もそういう答えかも知れませんです。
余計なお節介すみません。m(__)m
朝日新聞の記事を読む限り、ここも「企業がライターに依頼する時に守るべき指針」を公表した。
「DeNA問題でクラウドソーシング大手が新指針」
http://www.asahi.com/articles/ASJD85T27JD8ULFA02V.html?ref=mixi
「第三者の記事や写真を無断で転用したり、一部を書き換えて独自記事に見せかけたりする仕事の依頼を禁じる。違反すると会員登録を解除することもある。」
クラウドワークスはこれまでの指針では「著作権侵害などの恐れがある仕事の依頼を禁止する」としており、新しい指針では具体的な禁止行為を示した。
と言うことみたいです。
岡嶋昌之さん、情報ありがとうございます。
CWサイトでも確認しました(https://crowdworks.jp/press/?p=7020)
私としては、なんだこれは!?といった感じですね。
下のプレスリリースのタイトルからも読み取れるように、今回のDeNAの不祥事は、まったくの他人事になってます。
------------
クラウドワーカーがお仕事の単価や品質を評価できる「お仕事評価機能」をリリース
~クラウドワーカーの働く環境を向上するためのプロジェクトを開始、
仕事依頼ガイドラインの刷新とガイドラインに基づいた仕事内容のモニタリングも強化~
------------
“クラウドワーカーの働く環境を向上するためのプロジェクト”なんて書いてありますが、論点をごまかしてる。
そもそも評価しても、それがどう反映されるか本文を読んでも曖昧で効果やメリットが分からないし。
また本文中には下記の記述もあります。
------------
これまでも利用規約違反のお仕事に関するパトロールは行ってまいりましたが、
------------
これはウソ、あるいは言い逃れだよね。
これまでDeNAのパクリ騒動でクラウドソーシングの介在がさんざんいわれていて、“日本最大級(CWトップページ)”を名乗るCWが関係していないわけがない。
むしろ最大級を自認するなら、自ら率先してパクリ一掃のアクションを起こすべきなのに。
やる気の感じられない腰の引けたリリースで、とてもガッカリです。
はじめまして。12/8付でガイドラインが明確にされましたね。
https://crowdworks.jp/pages/guidelines/job_offer.html
しかしコレ、明らかな不備が見受けられるのは私の気のせいでしょうか?
外部サービスの規約違反などにより運営に影響を及ぼす可能性のある仕事
外部サービスの規約違反など正常な運営を妨げたり、影響があるような仕事の依頼を禁止しております。
<具体例>
オークションサイトなどの電子商取引サービスに、代理出品など手元にない商品の出品を依頼する内容の投稿。
外部サービスの利用規約等に違反する可能性がある内容の投稿。
Facebookページのいいねを促す投稿。
Twitterのフォローを依頼する投稿。
Gmailアカウントの作成を依頼する投稿。
はてなブックマーク登録を依頼する投稿。
YouTubeの再生を指示する投稿。
メルカリに関する仕事投稿。
NAVERまとめの作成投稿。
個人的には最後の「NAVERまとめの作成投稿。」がもっとも大きな不備と思っております。
正しくは「NAVERまとめ等のまとめ記事サイトへの記事の作成投稿。」とするべきで、「NAVERまとめ」だけでは名称変更などの抜け道を推奨しているようにしか思えません。
先ほどCW運営への問い合わせで、こちらについての説明と運営としての見解をお尋ねさせて頂きましたが、先が思いやられます。
まぁ、「自己責任でやるしかない」と思いますよ。
著作権法はそもそも定義が非常にややこしいですから。
著作権といっても「引用」(著32条1項)に定義があって、これに該当すれば「著作権侵害」にならないんですよね。
(著32条1項)
「公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その利用は、公正な慣業に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
さらに、(著10条2項)で下記の内容を定めてます。
「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作権に当たらない」
これは「引用」と判断されれば「著作権法違反」にならない!ということです。
「文章」の場合は内容を読んで判断しなければ「引用」に該当するか?否か?がわかりづらいのもあるでしょう。
ぶっちゃけ! 依頼者が「"引用"して・・・という意味で依頼しました」なんていうと話がややこしくなるんですよね。
読解力と適切判断が必要とされるので、完全な対応をするのが困難だと思っているのかもです。
「プロ」としてやるライターなら、「プロなんだから、仕事の内容の良し悪しくらいわかって当然」と考えているのかもしれません。
まぁ、基本こういうビジネススタイルで仕事をするのは「自己責任」なので。
ここの対応もそれなりになるんでしょうね。
皆さんに教えていただいたCW問い合わせ窓口からの返事がきました。
ここで「引用」してご紹介するのは真義に関わるので控えるとして、まさに用意しておいたテキストをコピペしただけのような、テンプレ感満載、内容の無いメールでした。
また、皆さん、コメントありがとうございます。
>kanzaki2_0703さん
CWがやっていることは、良くも悪くも「プラットフォーム」の範疇から出ないと思います。
だけど、町の不動産屋が責任持って物件を教えてくれるように、CWも責任とモラルを持ってほしいと思ってるんですけどね。現状は、単にスペースを開放してショバ代取っているだけ。最小のコストと人員で、最大限の利益を追求しているだけのように見える。それってDeNAの「キュレーション事業(笑)」と本質は同じですよね。
>岡嶋昌之さん
「人のフンドシで相撲取るな」っていうことだと教わりました、著作権のこと。相撲=収益を上げるビジネス、ですよね。
そう判断すると、DeNAのキュレーション何たらとかいう事業は全部アウトですよ。
っていうか、ネット関連の人はモラルが感じられない。ルール以前の問題。マッドサイエンティストが原爆を作っちゃうような、そんな怖さを感じる。今回の一件で少しでも是正されればいいんでしょうけど、DeNAがああなってからもその二番煎じのような募集があとを絶たないことを見ても、ムリでしょうね。
まぁ、著作権法の刑事責任は厳しいですからねぇ〜。
(著119条1項より)
「著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金等の刑事罰を受ける可能性がある。」
さらに、被害者が情報配信者(CWで依頼を受注して作業した)がこれらの罪責を問われるように!
告訴して刑事責任の追及することができますからね!
作業依頼を受けるライターとしては笑えない現実でしょう。
結局の所、「ご自身で法律(著作権法)を理解して自力で身を守るしかない」と思います。
まぁ、CW事務局に頼っていると大失敗をするかもしれないですから。
刑事訴訟になったらかなわないんで訴えられる前に被害者と示談交渉して解決される方が多いでしょうから刑事責任を問われない場合が多そうですけどね。
それでも示談金は結構高くつくでしょうから、自己防衛はとても大事ですね。
ついでに言うとこの「著作権法違反」は「未成年者でも責任を追求できてしまう」のですよね。
これは「民事法714条」で定めてあるのですが!
「親権者などの監督義務者が、監督義務違反として不法行為に基づく損害賠償責任を負う」
と言うことで100%ではないのですが、未成年者だから大丈夫とはならないです。
つまり、アルバイト感覚でやっている学生も例外になりませんし考慮されないですから。
まぁ、他にも
商品紹介レポートなどなら「景品表示法」、「不正競争防止法」
求人・求職サイトや出会い系サイトの場合、「職業安定法」や「出会い系サイト規制法」
などがありますからライターの方は十分に注意しないとえらい目に合いそうです。
よく仕事内容を確認してから請負う必要がありますね。
私も過去にDeNAのテストライティングに応募し合格となりましたが、見本記事の内容があまりにもスカスカでやり甲斐がなく、こんな記事を量産しても自分の技量が上がることはないと思い早々に辞退しました。
それから約8ヶ月、自分の専門知識がいかんなく活かせる分野に絞って活動を続けてきましたが、岡嶋さんのおっしゃることは良く分かります。
しかし、CW側が知らぬ存ぜぬの態度を取っているのは正直頂けないな、というのが本音ですね。
安くない手数料を抜いておきながら綺麗事を…という気持ちになるのは私だけでしょうか?
お気持ちはよくわかります。
ただ、法律上もここに責任の義務はないんですよね!
「当事者同士の契約」に介入すると、責任の一部をCWが持たなくてはならなくなる可能性がある為に、ここは関与してこないのです。
ですから、今後もあまり期待できないと思います。
私は昔、派遣会社の社員をしていた事がありますが、その当時の派遣会社の取り分はすごかったです。
直受けならまだマシでしたが!
それを考えると、クライアントもクラウドワーカーも仲介業者が1社なのでこれでもマシな方かもしれません。
まぁ、人それぞれですが自分は「自分の身を守る為、色々と法律の参考書籍を書い読みました。」
結構お金がかかりましたけど、「何が問題になっているのか?」を少し理解できました。
これでトラブルに巻き込まれる確率も少し軽減すると考えてます。
ここの利用規約は「CWの身の安全を守る事と一般的な法律について記載しているだけ」ですから
クラウドワーカーにとって、そのまま作業をすると随分と不利な条件で作業をすることになります。
可能であれば、クライアントと「追加契約書」を交わしておくと良いでしょう。
例えば、個人情報の取り扱い、著作権物の取り扱い等々の責任のあり方、所在など。
事前にクライアントと話をして、取りまとめて同意文書を作成して双方で同意の署名をしておかれると
あとで責任の所在などが明確になり多少でも身の安全を守ることができます。
打ち合わせに基づいた「作業範囲」も明記しておかれると無茶な作業を強制されなくて済みます。
少し手間ですが「契約書作成」の参考書籍が沢山出版されていますので、その中にはCDなどでサンプルが入っていますからそれらをベースに自分にあった契約書の雛形を作成されておかれると良いかもしれません。
結局の所、「法律で仲介業者の責任の範囲を規定していません」から自分で自己防衛する対策を検討しておく必要があるんですよね。
こう言う仕事スタイルは「自分の身は自分で守る」しかない!
そう自分は認識しています。
ユーザーのみなさまへ
クラウドソーシングは世に出て間もないものであり、世の中の人々の議論、学者による研究や判例の積み重ね等はまだまだ十分ではないと思います。そのため、クラウドソーシングに関しては多くの法的問題があり、それらの論点についても、複数の解釈や学説が出てくるだろうと予想されます。
※法の世界で「論点」とは、考え方が分かれる法的問題を指します。
そのため、以下にコメントする内容はあくまで「論点」に対する、私の個人的解釈となります。
岡嶋様のご回答に対して、コメントいたします。
>ただ、法律上もここに責任の義務はないんですよね!
「Yahoo!オークションに関する集団訴訟事件」(名古屋地裁平成20年3月28日判決)において、裁判所は次のように判示しています。
「本件利用契約は本件サービスのシステム利用を当然の前提としていることから、本件利用契約における信義則上、被告は原告らを含む利用者に対して、欠陥のないシステムを構築して本件サービスを提供すべき義務を負っているというべきである」。
「被告が負う欠陥のないシステムを構築して本件サービスを提供すべき義務の具体的内容は、そのサービス提供当時におけるインターネットオークションを巡る社会情勢、関連法規、システムの技術水準、システムの構築及び維持管理に要する費用、システム導入による効果、システム利用者の利便性等を総合考慮して判断されるべきである」。
※「信義則上」とは、民法1条2項の「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」とする「信義誠実の原則」に照らして、という意味になります。
クラウドソーシング事業とオークション事業は異なるものですが、共通点もあります。
そのため、クラウドソーシング事業者も利用者に対して、「欠陥のないシステムを構築してクラウドソーシングサービスを提供すべき義務を負う」可能性があるのではないでしょうか?
・IT pro(北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」 ヤフーオークションサイトの損害賠償訴訟(2) )
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080909/314477/
・IT pro(北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」 ヤフーオークションサイトの損害賠償訴訟(1) )
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080827/313484/
・IT pro(IT法務ライブラリ ネットオークションをめぐる法律問題(2))
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20081114/319293/
K090さん、ご回答ありがとうございます。
------------
クラウドソーシング事業とオークション事業は異なるものですが、共通点もあります。
そのため、クラウドソーシング事業者も利用者に対して、「欠陥のないシステムを構築してクラウドソーシングサービスを提供すべき義務を負う」可能性があるのではないでしょうか?
------------
このご意見、私も同感です。
オークション同様、クラウドソーシングも始まって歴史が浅く、社会や法律がキャッチアップできていないのが現状です。
派遣労働というスタイルに合わせて法整備がされてきたように、クラウドソーシングもこれから法整備がされるべきだと思っています。
だからといって、みんなでボーッとそれを待っているのではなく、特にCWのようなプレーヤー、しかも“日本最大級(CWトップページ)”を名乗るのであれば、自ら率先して市場環境の整備に当たるべき。必要であればこの機会に他社と話し合って、業界ルールを作ってもいいはず。
法律がないからといって小手先の「改革」だけですませようとしているCWの現状を見る限り、企業姿勢としてはDeNAのキュレーション事業と何ら変わらない。私が見る限り、CWがこの事業を社会的に価値あるモノに育てようという意識は、全く感じられません。
基本的な話ですが!
ヤフオクは「請負契約」でも「準委任契約」ではありません。
国の法律上、「請負契約」の場合は!「民法第632条」が適用されます。
これは請負業社が「全責任を請負う」と言うことです。
つまりCWにその責任の一部も請負う義務はありません。
「民法第632条」がなくならない限りご指摘のような対応を裁判所は行いません。
判例を調べられても明らかだと思います。
さらに、補足しておきますと! まで、ご丁寧に定めています。
(民法第644条)善替注意義務
(民法第634条、民法第637条)修補
644条で定めているのは下記の通りです。
「受任者(仕事を委託された側)は、委任の本旨に従い、善良な "管理者" の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」
仕事を委託された側が「管理者」として委任事務の責任を負う!と言うことです。
要は上記のようなことを法律で定めているので!
CWの利用規約に明記しなくても、CWは責任を負わないで良いわけです。
だから、そう言う対応要求は却下されると言うことです。
「自分の身は自分で守る!」ここでの仕事をするなら、多分これだけです。
今晩はです。
クラウドワークスにね、何を期待しているのでしょうって思っています。
あくまでも仲介役ですし、仮に違法行為でした。
私達にはね、何も関係されないんですけれど・・・。
記事とかそういう問題はあくまでもクライアント様とのやり取りの問題って思っています。
そう思わないとね、やっていけれませんから。
Mojio_kun様、キツい発言すみません。
ですけれど、CWにその様な考えは無いって思っていますし、それが現状ではないかなぁ?です。
おはようございます。
私の発言はスルーして下さい。
ただ、過去に相談所で間違えて記事を書いたものを記載してしまいました。
クライアント様からは、「敢えて砕いて書いて欲しい。」って言われ、私自身も良いかなぁで書いた記事があるのですけれど、
相談者にそれを送信してしまいました。
例えばですけれど、
ありがとうございます。
ありがとね。
みたいに書いて欲しいっていう理由です。
見事に今では「2ちゃん」に添付されて笑い者になっています。
CWに問い合わせても意味が無いっていう理由は、あくまでも、双方での解決っていう答えでしたから。
クライアント様がしっかりした相手ですなら、CWに頼っても意味が無いって思って記載させて頂きました。
あくまでも、仲介役ってその時実感しましたので、私自身はCWよりも、クライアント様を信じたいって思っています。m(__)m
不愉快な発言すみません。
ですけれど、記事を間違えた私自身も悪いのですけれど、2ちゃんは晒し者扱いさせて、CWも知らない顔が辛かった過去です。m(__)m
今では、きちんとした記事を書いていますけれど。
CWには余り期待は持たない方が良いって思っています。
お気持ちはね、私自身も同じですけれど、
自分自身が正しいって思う事をすれば良いって思っています。
相談内容が違う事は分かっていますけれど、過去のお話です。
自分自身がしっかり基盤を作って置けば良いって思っています。
私はそうしていますので、参考にはならないって思っていますけれど、こういう例もありますっていう事です。m(__)m
失礼します。m(__)m
岡嶋様へ
岡嶋様の下記のような表現により「クラウドソーシング事業者には、一切法的責任がない」と他のユーザーの誤解を招くのでは?と感じます。
>ただ、法律上もここに責任の義務はないんですよね!
>結局の所、「法律で仲介業者の責任の範囲を規定していません」から自分で自己防衛する対策を検討しておく必要があるんですよね。
つまり、岡嶋様としては、「クラウドソーシング事業者に一切法的責任がないわけではありません。たとえば、プロバイダ責任制限法など、クラウドソーシング事業者が負担しなければならない法律上の義務はあります。ただ、私の個人的解釈としては、考え方が分かれる幾つかの論点に関しては、クラウドソーシング事業者に法的責任がほとんどないと考えています。しかし、このような私の個人的解釈に反対する見方も存在しています」のような主旨の内容を表現されたいのではないでしょうか?
しかし、岡嶋様の上記のような書き方では、説明が短すぎて「クラウドソーシング事業者には、一切法的責任がない」ように読めてしまいます。私が何度かコメントしている理由の一つは、このようなことが気になるからです。
・IT pro(IT法務ライブラリ ネットオークションをめぐる法律問題(1))
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20081107/318742/
失礼ながら、具体的に商法何条で仲介業者の責任を定めてますか!
請負契約、委任契約でそのような条項は確認できていません。
条項に記述があるのであれば、具体的に何条で責任を定義しているか!
明示的に記載してもらえますか。
また、判例でそのような条例で罪を問われているならそれも提示してください。
みんな、対応できないから不満を言っているのだと思いますよ。
実際に民放でもIT基本法でも何も書いていないから、そのまま書いているだけです。
裁判というのは法令で定めていなければ控訴しても何の責任も問われないと思いますよ
請負契約でも委任契約であれ、定めているのは請負業者が全責任を請け負う。
ということです。
これは、弁護士の説明でも明らかですよ
もう一度書きますが!ヤフオクは「請負契約」でも「委任契約」でもありませんので論外ですよ。
K090様、現実問題、クラウドワークス自体には責任はありません。
何故なら、クラウドワークス自体が大元ではありませんからです。
責任を問われるってなれば、クラウドワークスの大元になります。m(__)m
残念ですけれど、これが法律の落とし穴なのです。
K090様
「法律」や「契約形態」を無視して味噌もクソもごっちゃにした発言はやめるべきだと思います。
周囲まで混乱させます。
K090様へ、
お気持ちは凄く分かります。
でも、責任はクラウドワークス自体にはないんです。
あくまでも雇われですから。
民事、刑事になった時に責任を問われるのはね、クラウドワークス自体を支えている大元の企業になってしまうんです。
クラウドワークスが出来る範囲、色々な項目も全て、クラウドワークスが作っていないっていう事なのです。
ですけれど、励まして頂きました事は、感謝しています。
ありがとうございます。m(__)m
サイトでもちゃんと書いてますよ。
http://www.weblio.jp/wkpja/content/請負_請負の効力#.E4.BB.95.E4.BA.8B.E5.AE.8C.E6.88.90.E7.BE.A9.E5.8B.99.E3.81.A8.E4.B8.8B.E8.AB.8B.E8.B2.A0.E5.A5.91.E7.B4.84
「請負人は仕事完成義務を負う(632条)」
つまり、全責任は受注者にあるんです。
岡嶋様の言っています通りになってしまうっていう意味が上の記載です。m(__)m
請負契約でも委任契約であれ、定めているのは請負業者が全責任を請け負う。
ということです。
これは、弁護士の説明でも明らかですよ
依頼者が責任を負うがそれを転嫁するということです。
依頼者が金銭を被害者に先に払ってからさらに払えと要求するという意味です。
論点1
クラウドソーシング事業者は、プロバイダ責任制限法におけるプロバイダとしての責任を負いますか?
私の解釈
クラウドソーシング事業者は、プロバイダ責任制限法におけるプロバイダとしての責任を負う可能性があります。
※参考サイト(ランサーズ・プライバシーポリシー)
http://www.lancers.jp/help/privacy
論点2
クラウドソーシング事業者は、クラウドソーシング利用契約における信義則上、利用者に対して、欠陥のないシステムを構築してクラウドソーシングサービスを提供すべき義務を負いますか?
※「クラウドソーシング利用契約」とは、クラウドソーシング事業者の利用規約に利用者が同意することで、クラウドソーシング事業者と利用者との間に成立する契約とします。
※「信義則上」とは、民法1条2項の「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」とする「信義誠実の原則」に照らして、という意味になります。
私の解釈
クラウドソーシング事業者は、クラウドソーシング利用契約における信義則上、利用者に対して、欠陥のないシステムを構築してクラウドソーシングサービスを提供すべき義務を負う可能性があります。
・IT pro(IT法務ライブラリ ネットオークションをめぐる法律問題(2)事業者が利用契約に基づいて信義則上負担する義務)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20081114/319293/
K090様
実際に、裁判してその発言を立証できますか?
なんども言いますが、周囲を混乱させるだけの発言はやめましょう
そんだけ確信があるなら、「やって見せて証明してください」
なんども言いますが、そんな判例はありません。
さらに、私が言っている条文を変更するような法律は存在しません。
岡嶋様
ご説明のため、論点1と2を例に挙げさせていただきました。
岡嶋様は下記のようにコメントされています。
>ただ、法律上もここに責任の義務はないんですよね!
>結局の所、「法律で仲介業者の責任の範囲を規定していません」から自分で自己防衛する対策を検討しておく必要があるんですよね。
このような表現ですと、「クラウドソーシング事業者には、一切法的責任がない」と他のユーザーの誤解を招くように思います。
たとえば、上記の論点1については、岡嶋様もクラウドソーシング事業者の法的責任を否定されないのではないでしょうか?そのため、「クラウドソーシング事業者には、一切法的責任がない」と誤解されるような表現は避けたほうがよいのではないでしょうか?
このようなことが私の申し上げたいことです。
特に、初心者の方に対しては、誤解を招かないようもう少し補足説明が必要だと感じます。
また、論点2に関していえば、多くの人の間で解釈が分かれる法的問題だと思います。解釈が大きく分かれる法的問題について、それぞれのユーザーが自分なりの解釈を持ち、法的議論を交わすのはよいことだと考えています。
ただ、その場合も初心者の方が見ることもあるわけですから、表現方法に気配りが必要ではないでしょうか。たとえば、自分の解釈を書くときでも、別の見方・別の解釈があることを示す必要があると思います。
K090様
解釈が分かれているのは、多分あなただけだと思います。
判例がある以上、普通は解釈は同じだと思います。
あなたの解釈の通りの判例があるなら提示してください。
くらうど業者の責任を否定する判例はありませんから確定していません。
今回はうえるくが自発的に損害補填するといっています。執筆者に後日負担させるかは不明です。
てか、契約形態を請負契約とか委任契約と定めている時点で、確定だと思います。
ここは責任なんて持つ気はありません。
もし、その気があるなら利用規約にでも書くでしょう
他のユーザーのみなさまのためにも「判例」について、ご説明させていただければと思います。
「判例」という言葉は、一つの意味だけでなく、さまざまな意味で使われています。たとえば、個々の裁判そのものを指し、「○年○月○日の判例」ということがあります。また、過去のある事件において、最高裁判所が示した法律的判断のことを指すこともあります。
法律の勉強では、「条文・判例・学説」の3つが大切と考えられています。この3つはそれぞれが無関係に存在しているわけではなく、相互に関連しあっています。
たとえば、判例を受けて条文が改正される場合もあれば、学説の意見を採用して最高裁判所が判例を変更することもあります。
また、「拘束力のある判例としての意味があるのは、最高裁判所によるものに限られる」と考えられています。最高裁判所は全国にある下級裁判所の判断を統一する機能を担っていると考えられます。
下級裁判所の判断に拘束力は認められていませんが、色々な法律の議論において参考にされることがよくあります。
また、最高裁判所の判例に拘束力があるといっても、成分法のような絶対的な拘束力ではなく、事実上の拘束力があるに過ぎないと考えられています。
裁判官はいつでも必ず最高裁判所の判例に従わなければならないわけではなく、個々の事案によっては、最高裁判所の判例と異なる判断をする場合もあります。
このように、最高裁判所の判例であっても、常に変更される可能性があるといえます。そして、変更される可能性の低い最高裁判所の判例を「強い判例」、変更される可能性が高い最高裁判所の判例を「弱い判例」と呼ぶことがあります。
たとえば、同じ判断が長年に渡って繰り返されて「確立した判例」になっている場合やその時の社会情勢に合致して特に有力な反対論もないような場合、「強い判例」といえるかもしれません。
他方、学者や実務家や世の中の人々から反対が多い判例は、「弱い判例」といえるかもしれません。
仮に、今までにクラウドソーシング関連の判例が出されていたとしても、「確立した判例」とまでなっているとは考えにくいです。世の中の人々が、新しく登場したクラウドソーシングに関して持つ意見はさまざまだからです。そのため、多くの人々が、解釈の分かれるであろう「論点」に関し、自由に意見を述べたほうがよいと思います。
委任契約だの請負契約だのと言っている時点で、責任は全部受注者が持つと言っているのと変わりません。
K090様
ですから、過去にあなたのいう解釈で判決された実例はありますか?
と言ってます。 実例もないことを可能なようにいうのはやめたほうがいいです。
法律で定められている条文がある以上、それを基に審議されるんです。
CWに積みがあるかどうかって話は、マネーロンダリングしている、例えばカジノとかに罪があるのかって話でしょう。
カジノはマネーロンダリングをしますって商売をしてるわけではなく、行われるのはあくまでも賭博。賭博が許可されている国なら合法です。でもカジノは、マネーロンダリングするために賭け事の形を取る人々からの謝礼が最も大きな収入で、これがないとビジネスモデルとして成立しないという話があります。つまりこうなるとカジノとはマネーロンダリングをしてなんぼ(マネーロンダリングしてこそのカジノという事になります。
こうなると、カジノの存在はマネーロンダリングと密接な関係にあり、カジノは、反社会的な組織とも言えるでしょう。
CWは人材を提供しただけ。しかしその経緯を見ると、CWが当然わかった上で、ちょうど良さそうなワーカーを斡旋していたとすれば(していたんでしょうが)それは、DeNAの問題を後押ししていた事も明白で、CWがなければ今回の問題も起こらなかったと言えます。罪がないとは言えないでしょうね。
おはようございます。
昨日、CWからこんな募集メールが流れてきてましたね。
-----------
♡【大量採用中!!長期歓迎!!】“女性向けファッションメディア“を執筆するライターを募集! 長期継続・大量執筆可能【1記事900円など】♡
〜中略〜
*.。.*.。.*.。.*゚執筆いただく記事のイメージ*.。.*.。.*.。.*゚
★以下のページをご覧頂ければ、作成していただく記事のイメージがつかみやすいかと思います。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://mery.jp/
(※mery.jpはこの案件とは関係のないサイトです!)
-----------
ちなみに公開日は12月11日。
文字単価は0.4円 〜 0.7円。
もうね、脱力ですよ。
まだこんな募集流してる。Meryなんて、とっくに公開中止になってるのに。
発注する方も、それをそのまま流すCWも、チェックしてないのがバレバレ。
先日のCWからのリリースでは、募集情報を精査することには言及してなかったら、当然といえば当然。
百歩譲って、情報が膨大なのでいちいちチェックなんかしていられないのかもしれない。
でも、そんなときはシステムで工夫して品質管理するのがプラットフォーマーたるCWの仕事だと思うんですけどね。
極論すると、言葉巧みに人殺しさせるような案件情報があって、それがそのまま流されることだってあり得るでしょ。今のままなら。
たまたま、それを見たワーカーがまじめに“仕事”してしまったら・・・わずか数円のギャラと、CWの手数料だけで、人が殺せてしまう!? ゴルゴ13は失業??(笑)
万一そうなったとしても、殺人依頼の情報を流したCWの罪は問えないわけでしょ。
その程度の無責任な仕組みなわけですよ。
「クラウドファンディング」には、夢を実現したい人と、それに共感して支援したい人を結びつけるという意義があると思っています。
ですが、おなじ“クラウド”でもクラウドソーシングには、事業としての意義とか価値とかあるんですかね。
無責任なシステムだから社会にとっても無価値でしかない、ということかも。いまのままでは。
そんな感じで、ウェルクをはじめとする一連のDeNAの問題では、クラウドソーシングに関して新しい認識ができましたね。
さ、仕事しましょ。月曜日だし。
皆さん、ここまでいろいろなコメントを頂き参考になりました。ありがとうございました。
K090様
あくまでもご参考程度で。
>論点1
>クラウドソーシング事業者は、プロバイダ責任制限法におけるプロバイダとしての責任を負いますか?
これについては、「負う可能性がある」ではなく「負う」が正解でしょう。
プロバイダ責任制限法は、有り体に言えば「発信者個人情報の提供措置」に関しての法律と言えます。
つまり、ワーカーおよびクライアント間で法的問題が発生した際に発信者情報の開示請求に応じる責任があり、ワーカーおよびクライアントが法的根拠に照らして著しく権利侵害などをしているのであれば、発信者情報を開示する義務というものがあります。損害賠償請求において、クラウドワークスは最終的に発信者情報を開示すれば賠償責任を軽減または負わないという事になります。
なお、発信者情報の開示請求のフォーマットにつきましては誰でもダウンロード出来るようになっています。
http://www.isplaw.jp/d_form.pdf
詳しくは、以下のサイト(プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト)をご確認ください。
http://www.isplaw.jp/
基本的に、ワーカーとクライアント間での法的トラブルはこの発信者情報の開示請求を利用して紛争解決を行います。
>論点2
>クラウドソーシング事業者は、クラウドソーシング利用契約における信義則上、利用者に対して、欠陥のないシステムを構築してクラウドソーシングサービスを提供すべき義務を負いますか?
これについては挙げられている例でも裁判所側は原告側の主張を退けていますね。
(抜粋)
「利用者側は,この契約について,仲立ちとしての性質を有するものであって,請負契約や,準委任契約と類似の契約であるので,請負契約から導かれる仕事完成義務(民法632条)や,準委任契約から導かれる善管注意義務(民法656条,644条)を負担するものであると主張しましたが,裁判所は以下のように判示してこの主張を排斥しました。」
クラウドワークス側のシステム構築において、契約関係の信義則上の義務を負うとしても「欠陥のないシステムの構築」には限界があると判断されるため、あくまでもクラウドワークス側の責任は「業務委託契約を行う際に通常必要となる注意義務を利用者側が行う」という前提の元に限界が決められると理解するべきでしょう。
つまり、原則的には利用者(ワーかおよびクライアント)が業務委託契約を締結するにあたり、相当の注意義務を負っているというのが大前提であり、クラウドワークスはこの相当の注意義務を払った契約であることを前提としてシステムを構築すべき責任があると言えます。
そういった意味で考えれば、クライアントの入金後に作業を開始するなどのトラブルを防止するアナウンスなどはされており、通常利用者が業務委託契約の性質を知り、クラウドワークスの利用規約を理解した上で利用しているのであれば、トラブル防止の措置としてはクラウドワークス側は必要な措置を講じていると理解できるので、システム構築上の賠償責任を追求するのは難しいかと思います。
つまり、クラウドワークスは「欠陥のないシステム構築」を行う義務はあるが、それは「利用者が業務委託契約の性質や契約における相当の注意義務を払うことが前提で構築されていれば足りる」と理解出来るので、現時点でクラウドワークス側のシステム構築における賠償責任の追求は非常に難しいと言わざるを得ないと思います。
【総括】
結局のところ、現時点では受注者側が相場が低いというのであれば仕事を請けない(要するにネットストライキ)という事も大事かと思います。単価が低い案件に募集が集まらなくなれば、発注者も発注先を見失うので、自分で何とかしなければならなくなります。一番大事なのは、発注者も受注者も双方が「生活するのに最低限必要な単価とはいくらか?」というのを意識して受発注の契約を考えるということが大事なのではないかと思うんですね。
発注者は発注先が無くなったら困るのであれば、待遇改善を考えて現サービス設計を考え直す必要がありますし、受注者は自分が生活していく最低限の作業単価を発注者に求めるというのも大事です。そうしていくような意識を持たない限り、法律では保護する限界もありますので、マナーやモラルという面で自分たちで向上させていくという意識が大事なのではないかと私は思います。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
(※法的見解に関してはあくまでも個人の見解です)
Mojio_kun 様
大分話が逸れてしまっていますが、現時点でクラウドワークス側に責任を求めるのは難しいと思いますが、間違いなくWelqの余波は広がっているとは思います。あとは、最終的にWebメディア側が自分のサービス利益に照らし合わせて、サービス設計を見直ししてエンドユーザーに対する情報発信者のマナーやモラルというものを含められるか否かというところになってくるかと思います。
法的云々の話は、また別の個人ブログや署名を集めるなら署名サイトなどで発信してもらうのが良いと思いますが、今回のWelqをはじめとするWebメディアやキュレーションサイトの管理者には是非ともサービス設計を見直して欲しいと思います。
白河弥生さん、コメントありがとうございます。
私もそう願いたいです。
でも、↑で私が書いた募集の現状を見たり、これまでの経緯を見る限り(まだ短期間ですが)、
情報(パクリ記事?)を発信するキュレーション(盗み屋?)サイドも、その事業(悪行?)をサポートするクラウドソーシング(中抜き屋?)サイドも、改善する気持ちはあんまり無いみたいですね。
かえって、DeNAというビッグプレーヤーがいなくなったおかげで、他の“キュレーション(笑)”がこれ幸いとばかりに勢力拡大を目論んでる、CWもそれに手を貸しているという風情が僕には感じられます。
改善するつもりはないと思います。
ドル箱ですから。
ユーザー離れが起これば、変わると思いますが。
それでもDeNAがいなくなることは大きいでしょう。(本当にいなくなればね)
まとめサイトから客が離れ、別のビジネスモデルが出てくれば、変わるでしょう。
このビジネスモデルは薄利多売なので、ある程度資本があるところがやらないとうまみがないです。
小口のところは細々とやってると思いますが、それだけでは大きなムーブメントは作れないでしょう。
まあ、潮目が変わったと思いたいですけどね。
CWもかつてのように売れてるわけではなくて、売り上げ不振に悩んでいると言いますし。
ningyoutukaiさん、コメントありがとうございます。
ホント、そうですね。
これで潮目が変わって、真にユーザーのためのメディアができたり、それによってライター全体の地位向上につながったりすればいいんですけど。ムリかなぁ。。。
ふと気付いたら、CWではこんなスローガンをうたってますね。連絡メールのフッタあたりに記載があります。
「21世紀の新しいワークスタイルを提供する」
私としては↓じゃないか、と思うんですが。
「21世紀の新しいぼったくりスタイルを提供する」
ま、これ以上罵詈雑言かますのは私としても生産的ではないので、この板に書き込むのはこれを最後にしたいと思います。
皆様、ありがとうございました。
・IT pro(IT法務ライブラリ ネットオークションをめぐる法律問題(3))
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20081125/319811/?rt=nocnt
オークションサイトでは、「トラブル事例等の紹介、サービスを利用する際に注意すべきポイント等を掲載したページ」を設けているようです。
クラウドソーシングでもこのようなページを設けることにより、少しはトラブル予防に役立つような気がします。そのため、できればこのようなページを設けてくれるよう、要望書を送ってみようかなと考えております。
ただ、私は以前にもこのような要望書を書こうとして挫折した経験があります。「クラウドソーシングのトラブル事例集」を書こうとすると、けっこう難しかったです.....。
まず、私としては厚生労働省へ提出予定の「クラウドソーシングの働き方改善への要望書・第2弾」を完成させたいと思っております。その後、できれば「トラブル事例集ページ作成への要望書」を書いて、クラウドワークスに送ってみるつもりです。
「トラブル事例集ページ作成への要望書」について、ご意見・ご要望等がございましたら、下記のメールアドレスまでお送りいただけましたら幸いです。すぐにご返信はできないかもしれませんが、お送りいただいた内容について、ご返信させていただきます。
pandaclub2200☆gmail.com(☆はアットマークです)。
Hi,
上場企業であるCW社のコンプライアンス部門、いい人材いないですね。そもそもビジネスモデル自体
アメリカのウェブ&、豪州のFleelance.comの模倣、まさにコピペ。
ⅰ当方も以前は「案件に違法性がある」でリポートボタンクリックした。しかしあまりにも多い、なぜAI
入れてカットしないのか。
CW社、目を覆う違法案件を「お仕事探す」上にパブリックに放置。
アダルトビデオ出演、ポルノサイト導入、ステマ支援。
ⅱワーカー側もかなりもった偽造プロフィール。
ⅲCW社、社内人材を厚くしないと。リクルート社の人材の薄さに酷似してる。OICバッハ会長の能天気
に引けを取りません。
Regards