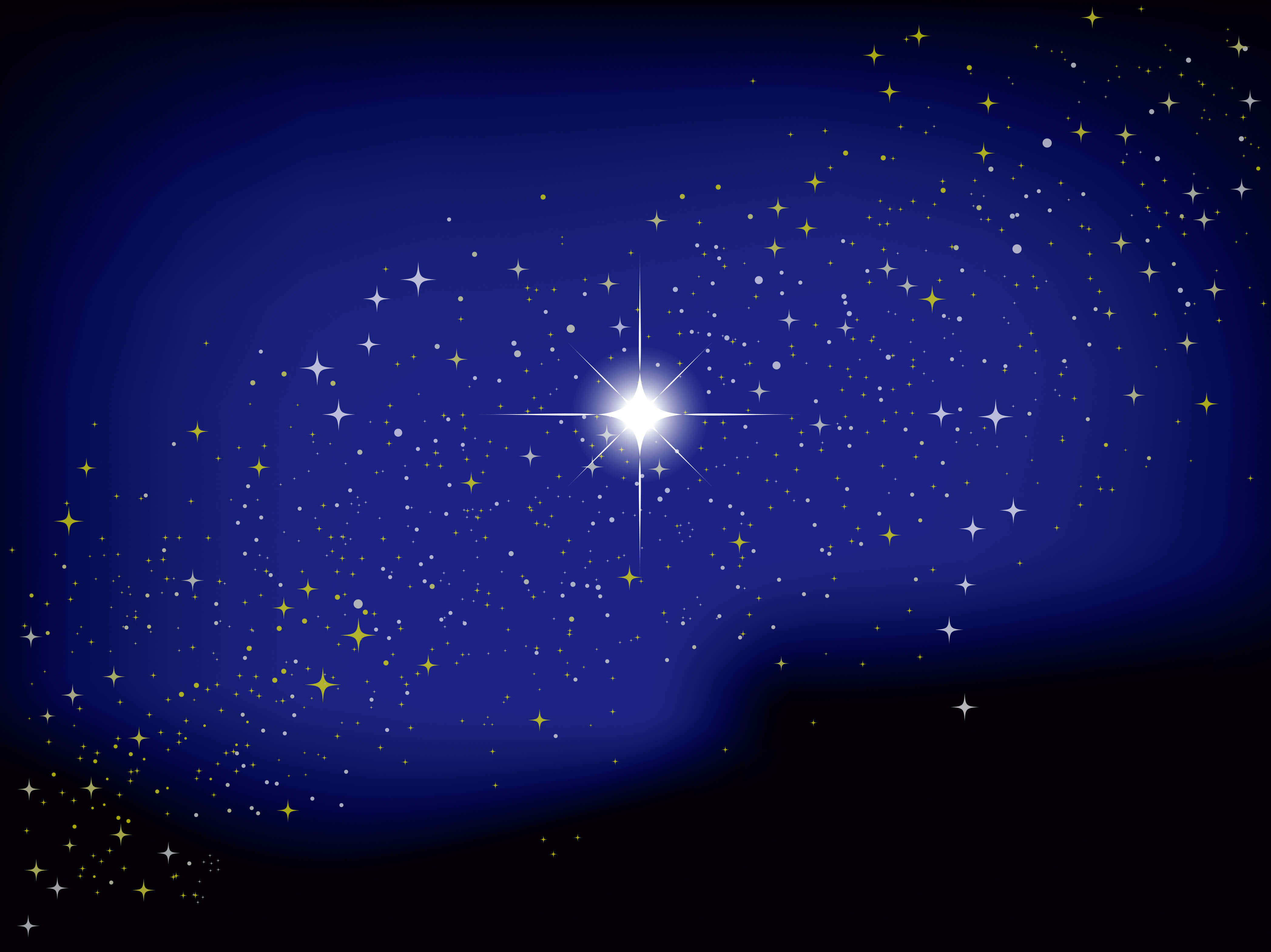「自分の店を持ちたい」という夢の実現のために学校に通ったり修行をしたりすれば、飲食店開業はもうすぐです。では、飲食店の開業時には具体的にどのような準備が必要になるでしょうか?飲食店開業に必要な資格や開業資金、届出や申請、補助金・助成金、開業時のおすすめ販促ツールをまとめて紹介します。
目次
飲食店を開業するのに必要な資格は?

飲食店を開業するとき、どのような資格が必要なのかご存じですか?飲食店の開業では「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つが必要です。
食品衛生責任者
飲食店や食品を販売する小売店を開業する場合、「食品衛生責任者」の資格保持者は1名以上在籍しなくてはなりません。食品衛生責任者の主な仕事は、店舗の衛生管理を行い、従業員に対して衛生管理方法の指導や徹底、管理をすることです。
資格取得をするためには、各都道府県の保健所などで公衆衛生学や食品衛生学など、計6時間の講習を受講します。費用は全国共通で1万円(教材費込み)。交付された食品衛生責任者手帳は、保健所に営業許可申請を提出する際に必要です。できれば飲食店を開業する約3カ月前には取得しておきましょう。
防火管理者
店舗の収容人数が30名以上になる場合は「防火管理者」が必要です。資格取得には、各地域の消防署などで日本防火・防災協会主催の講習を受講する必要があります。
延べ面積が300㎡以上の場合は、2日間で約10時間かけて防火管理訓練や教育、消防計画などの甲種講習を受けなくてはなりません。面積が300㎡未満の場合は、1日5時間で甲種の基礎的な知識、および技能を学ぶ乙種講習を受けます。費用は甲種で7,500円、乙種で6,500円です。
調理師免許は必ずしも必要ではない
意外に感じるかもしれませんが、飲食店開業のときに国家資格である調理師免許取得者は必要ありません。ただし、調理師免許があれば調理の知識を身につけることができ、調理師免許取得者がいることで店の信頼度も向上します。なお、調理師免許がある人は、食品衛生責任者の講習が免除となります。
飲食店の開業に必要な届出や申請は?

飲食店営業許可申請
食品調理や飲食する店を営業する場合は、必ず「飲食店営業許可申請」を保健所に提出しなくてはなりません。申請には店舗見取図や都道府県によって異なる手数料、食品生成責任者手帳などが必要で、店舗が完成する10日前までには提出するようにします。厨房機器、手洗い場、換気扇など設備面で細かな決まりがあるため、可能であれば着工前に店舗設計者と共に保健所に出向いて相談したほうが安心です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜0時以降も酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業届」を警察署に提出しなければなりません。ただし、主食と認められる牛丼やラーメン、パスタなどをメインで提供している店舗は届出が不要とされています。提出物は、店舗周辺の見取図や店内詳細図面、求積図、営業許可証、賃貸契約書のコピーなど。多種で煩雑なので、難しければ行政書士などの専門家に作成依頼をしましょう。
火を使用する設備等の設置届
火を使用する設備などを設置する場合、その管理者が存在することを証明する「防火管理者選任届」のほか、「火を使用する設備等の設置届」、「防火対象設備使用開始届」などを消防署に提出しなくてはなりません。
開業届/青色申告承認申請書
個人事業として飲食店を開業する場合は、税務署に行って「開業届」を提出します。また、最高65万円の控除を受けられる青色申告にする場合は、同時に「青色申告承認申請書」も提出しておきましょう。前者は事業開始から1カ月以内、後者は2カ月以内に提出しなくてはなりません。
飲食店の開業資金の目安とは?

飲食店の開業資金は、立地や店の規模、ジャンル、設備や内装のグレードなどにより異なります。おおよそ1,000万円が目安といわれていますが、内訳は以下のとおりです。
・設備資金:内装工事費、厨房機器、食器ほか消耗品費など
・運転資金:最低でも2~3カ月分の資金
いわゆる居抜き物件などを活用すると費用を抑えることができますが、それでも店舗物件の場合、一般的には賃料の10カ月分ほどの保証金が必要となり、これがもっとも大きな出費となります。開業を考えている不動産相場を確認しておき、おおよその目安を把握しておいてください。せめてこの不動産取得費を自己資金でまかなえると、そのあとの経営が楽になってくるはずです。
資金調達方法としては自己資金のほか、日本政策金融公庫等金融機関からの借入、創業補助金の利用、商工会議所の小規模事業者持続化補助金の利用などが挙げられます(補助金や助成金については次章でも紹介します)。さらに場合によっては親族や知人から借りるという手もあるでしょう。借入の場合、なるべく金利負担の少ない融資を選ぶことが重要です。
飲食店開業で使える助成金・補助金

飲食店を開業してもすぐに軌道に乗せることは難しいため、経営の費用だけでなく、経営者自身の生活費も考えておかなければなりません。このような時に使えるのが補助金や助成金です。金融機関の融資とは違って、返済義務がない「もらえるお金」です。ただし申請期間などには定めがあるので、あらかじめよく調べた上で申請申込を逃さないようにしてください。
創業助成金(東京都中小企業振興公社)
この創業助成金は都内での創業限定ですが、創業を予定している、もしくは創業して5年未満の人のうち一定条件を満たす場合に最大300万円が支給されます。詳細は東京都創業NETのホームページをご覧ください。
創業補助金
創業補助金は、株式会社電通が経済産業省中小企業庁からの交付決定を受けて実施しています。産業競争力強化法に基づいた認定市区町村での創業のみが対象となり、第11回認定申請予定となる2019年12月現在、19都道府県のうち49市町村が認められています。平成29年度の申請受付は終了していますが、創業・事業継承補助金のホームページはこちらから見られます。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、日本商工会議所が運営している補助金制度です。商工会議所の管轄地域内にて事業を行う小規模事業者が対象で、最大50万円が支給されます。詳細は小規模事業者持続化補助金のホームページをご覧ください。
飲食店の開業におすすめの販促ツール

経営を早く軌道に乗せてキャッシュフローを安定させるためには、なんといっても集客がキモです。開業を告知して集客につなげるためには、下記のようなツールを開業前に用意しておきましょう。
ホームページ
チラシやDM、SNSなどでお店のオープンを知った人が、最初に検索して見るのは自店のホームページです。最初は無料ツールでホームページを作成して、人気メニューや利用者のニーズが把握できるようになったら、お金をかけてしっかりとした内容にリニューアルすることがおすすめです。
ホームページに入れるべき内容や、作成での料金相場はこちらの記事をご覧ください。
関連記事:飲食店のホームページの必要性は?制作にかかる料金相場や作り方は?
SNSアカウント
自店のTwitterやInstagram、Facebook、LINEアカウントを開設し、できるだけ更新をするようにして情報発信を行います。インターネットやスマホが普及している今では、利用者からの拡散が期待できるこれらのSNSを有効活用することも店舗誘引のカギとなります。
ポイントカード
飲食店では固定客を増やすことが重要ですが、その「ファン」を増やして来店回数を上げるためにも、ポイントカードやスタンプカードなどを用意しておきます。スマホに収納できるスタンプカードもあるので検討してみましょう。
飲食店での集客イベントやキャンペーンのアイデアは、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:飲食店の集客方法とは?客数を増やすには何をするべきか徹底解説!
DMやチラシ
周辺住民や駅前など、人通りの多いところでのチラシ配付や見込み客へのDM発送は、ネット情報が届かない高齢者世代などもカバーすることができ、地味ながらも効果的なツールです。
チラシ作成のコツや作成方法はこちらの記事をご覧ください。
関連記事:飲食店のチラシ作成のコツは?効果を高めるデザインや作成方法を解説
販促ツールを手軽に制作する方法

販促ツールの制作に関するノウハウや経験がなく、どうしても内製できないならば、ぜひ外注することも検討してみてください。ホームページの制作やSNSなどを効果的に利用するには、専門家の知識とノウハウが必要です。自店のスタッフでは対応できない場合は積極的に外注し、その外注先としてクラウドソーシングの利用も検討してみましょう。
クラウドワークスなどのクラウドソーシングサービスには、ホームページ制作や魅力的なチラシ制作に精通した人が多く登録されています。開業準備で忙しいと、つい販促ツールを忘れがちですし後回しにしがちです。外注ならばスピーディーな完成も期待できるので、オープンまで時間がない時でもぜひ利用してみてください。
まとめ
夢だった自分の店をいよいよオープンする段階になると、理想が先走り、なるべく早く開店したくなるものです。しかし、飲食店の開業には資金問題や各種申請、ツール制作など、たくさんの事前準備が必要となります。オープン後に慌てないためにも、必要なことはリスト化して完了させ、安心して開業できるよう準備を進めてください。